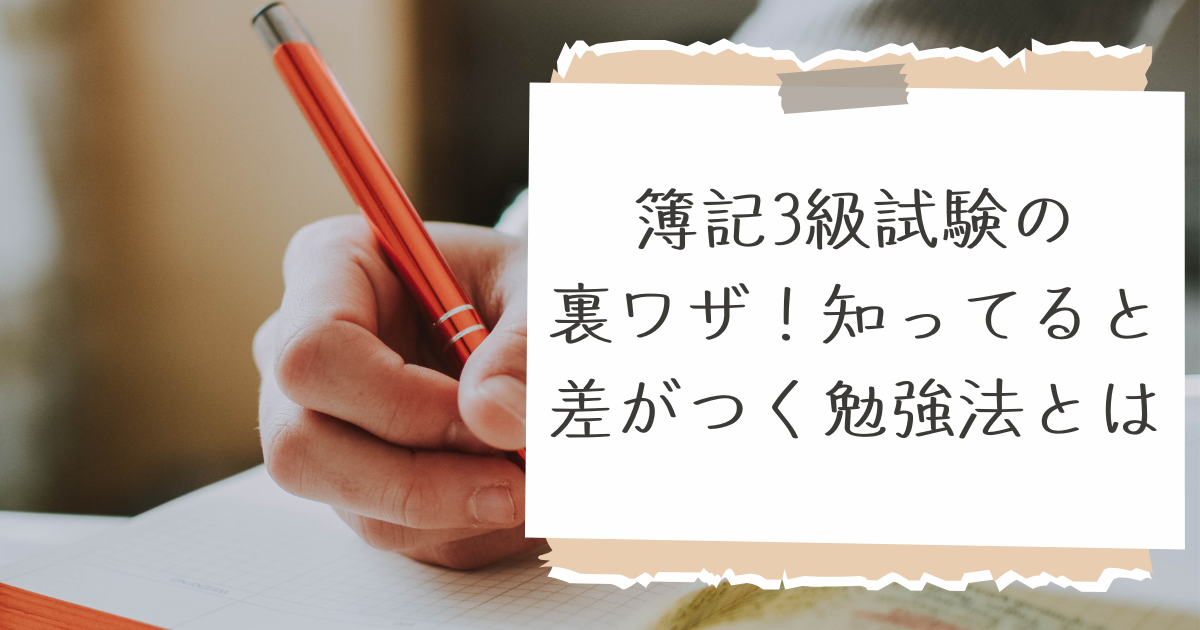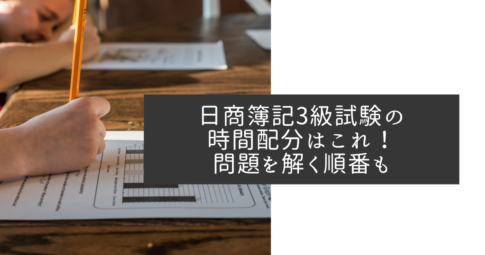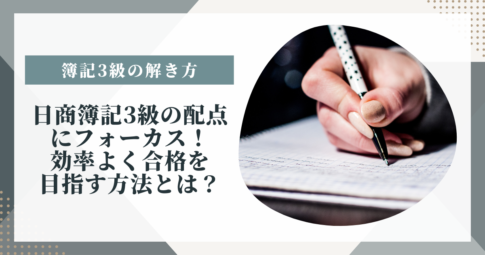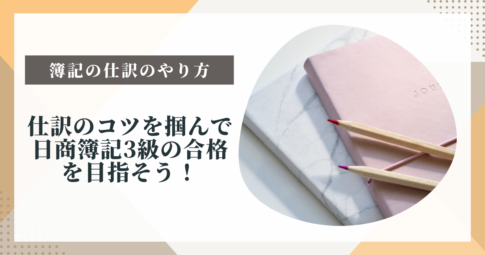はじめて簿記の勉強をすると、知らない用語や簿記独特のルールに翻弄されることになります。
覚える勘定科目もたくさんあり、仕訳のルールや簿記独特の癖みたいなものにも対応していかなければなりません。
また、1つの単元を進めたり問題集を解いたりするのにもかなりの時間を要します。
そうすると、「何か効率よく勉強を進められるような方法は無いかな?」とか「劇的に効果をあげるような裏ワザのようなものはないかな?」という思いがフツフツと湧いてきます。
ここでは簿記3級の対策に役立つような便利な裏ワザをいくつかご紹介したいと思います。
私自身も簿記3級の対策をし始めてから、これらの裏ワザを使ってかなり試験対策の時間を短縮することができました。
今回お伝えする内容を駆使して、効率よく簿記3級の試験を突破していきましょう。
ただ本当は、小細工をするよりも実際に問題演習を繰り返した方が力は付きます。
なお、公認会計士に興味がある方は、公認会計士専門予備校の「CPA会計学院」の資料請求がおすすめです。

合格者占有率が66.7%と圧倒的
【無料】CPA会計学院の資料請求をする目次
簿記3級の問題集を解くときに便利な裏ワザ3選【仕訳のコツ】
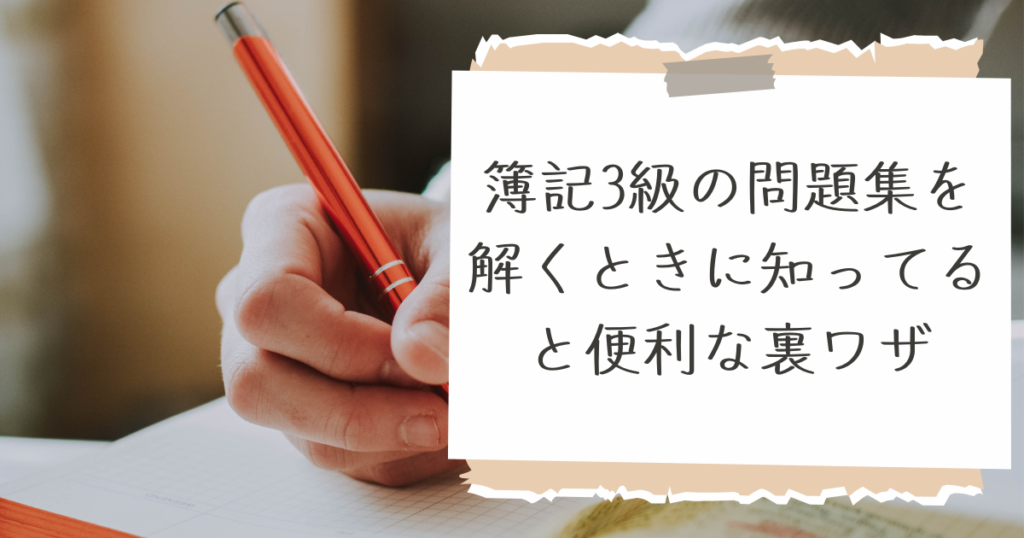
最初にお伝えする裏ワザは、簿記3級の問題集を解くときに知っていると便利な以下の3つの裏ワザです。
- 勘定科目を省略する
- フリクションのボールペンを使う
- 電卓の桁下げキー《→》を活用する
それでは順番に見ていきましょう。
勘定科目を省略する
問題集を解く際は、勘定科目を省略して書くと問題を解くスピードが劇的に上がります。
簿記の勘定科目は漢字で表記するものが多く、書くだけでかなりの時間を要します。
ただし初学者の場合、この裏ワザを使用する前にまずは正式名称による勘定科目をきちんと覚えてから省略して書くようにしましょう。
勘定科目がうろ覚えのまま省略表記をしてしまうと、勘定科目の意味が把握できず内容もチンプンカンプンとなってしまいます。
それではイメージしやすいように、いくつか例をあげてみます。
| 元の単語 | 省略後 |
|---|---|
| 「売掛金」 | 「売×」や「U×」など |
| 「買掛金」 | 「買×」や「K×」など |
上記のように省略することが多いようです。
ちなみに、この省略の仕方には何か共通のルールがある訳では無いので覚えやすい省略表記を使いましょう。
ちなみに「×」は四則演算の掛け算の記号を使って「掛」の漢字を省略したものです。
「U」や「K」は売掛金と買掛金の日本語読みでのアルファベット頭文字ですね。
けれども、あまりに勘定科目を省略しすぎると「あれ?省略したこの勘定科目ってなんだっけ?」ということになりかねません。
最初のうちは「売×」や「買×」のように、勘定科目の一部の漢字が入った省略表記を使っていく方が思い出しやすいです。
段々と慣れてきたら、「U×」や「K×」を使って問題を解くスピードをアップしましょう。
簿記3級の勉強をし始めると、最初はかなりの量の勘定科目に圧倒されることと思います。
簿記の学習に慣れていないと何もかもが初めて目にする用語であり、聞き慣れない勘定科目を覚えるだけでも精一杯でしょう。
さらに各勘定科目には決まったホームポジションもあり、それらのルールを覚えるだけでもかなりの苦労を要します。
そして、ようやく内容を理解して問題集に取り掛かってみると、大問をひとつ解くだけで想像以上に時間がかかることにも気付きます。
ぜひこの勘定科目を省略するという裏ワザを使って、問題を解くスピードを上げて効率よく試験対策を進めていきましょう。
紹介した省略表記のほかにも沢山の勘定科目の省略方法がありますので、興味があれば調べてみてくださいね。
フリクションのボールペンを使う
次に紹介する裏ワザは、文房具の一つ、フリクションのボールペンを使うといった裏ワザです。
フリクションのボールペンであれば一度書いた部分を摩擦消しゴムで消せるので、消しカス等も発生しません。
仮に普通のペンを使って繰り返し問題集を解こうとすると、事前に何枚かコピーを取っておき、そこに鉛筆やボールペン等で記入をすることになります。
家にプリンタがあればすぐにコピーできますが、問題集は大体冊子の形状になっているので、蓋をあけてガラス面に押し付けて印刷できるようなスキャナ一体型の複合プリンタ等に限られます。
なお、蓋などが無い単に印刷できるだけのプリンタだと、問題集をはさんでコピーすることができません。
もしくは、コンビニ、学校、職場の大きなコピー機を使えば印刷に苦労することはないかも知れませんが、コピーするのに毎回多少の費用がかかります。
また、家で用紙が足りなくなってしまうと、再度コピーを取りに外出しなければなりません。
それならばと、鉛筆を使用したとしても書いた後に消しゴムで消すと大量の消しカスが出てしまいます。
簿記3級の問題集を解いてみると分かると思いますが、試算表や精算表、損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)の表を埋める問題などは、一般的に問題集の穴埋め答案用紙をコピーすれば繰り返し使えるようになっています。
フリクションのボールペンを使えば直接書き込んだとしても、すぐに消せるのでわざわざコピーを取る必要はありません。
もし、大量に記入したものを1ページずつ消すのが億劫であれば、ドライヤーやアイロンをあてるだけでもいっぺんに文字を消せるので気になる方はこちらも試してみてください。
ただし、極端に近づけすぎたりあてすぎたりすると、紙が焦げてしまったり火事につながったりする可能性もあるのでその点はお気をつけください。
電卓の桁下げキー《→》を活用する
簿記の試験では電卓の操作が必須です。
電卓の一部の機能を知ってるだけで、簿記3級の問題を解くのが劇的に速くなります。
ところが、小学校や中学校の義務教育で電卓の使い方をしっかりと習った記憶がある人は少ないのではないでしょうか。
電卓には定数計算機能や独立メモリー機能など、使いこなせれば物凄く便利な機能があります。
ここではその中でも、シンプルでとても便利な機能にもかかわらず、意外と知られていない桁下げキー《→》について解説します。
ちなみに、桁下げキーは電卓のメーカーによって《→》となっていたり、《▷》となっていたりするようです。
まず、桁下げと聞くと小難しく感じるかも知れませんが、電卓の桁下げキーはパソコンでいうBack spaceキーと同じような役割をすると思ってもらって差し支えありません。
スマホの日本語入力にも1文字前の文字を消す「×印」を囲ったようなボタンがあるかと思いますが、そちらも似たような役割を果たします。
たとえば、「1,000,000(百万)」と打つつもりが「10,000,000(一千万)」と打ってしまった場合、またクリアキーを押して最初からやり直すのは億劫です。
もし、「10,000,000(一千万)」と打ってしまったら、桁下げキーを一回押せば、きちんと「1,000,000(百万)」と訂正されます。
これを知っているか知らないかだけで、最初から打ち直す手間が省け、多少電卓を打ち間違えても劇的に問題を解くのが速くなります。
今までこの電卓の桁下げキーを使っていなかったという方は、普段から積極的にこのボタンを使って問題を解いていきましょう。
合格点を超える(70点以上)ための裏ワザ3選
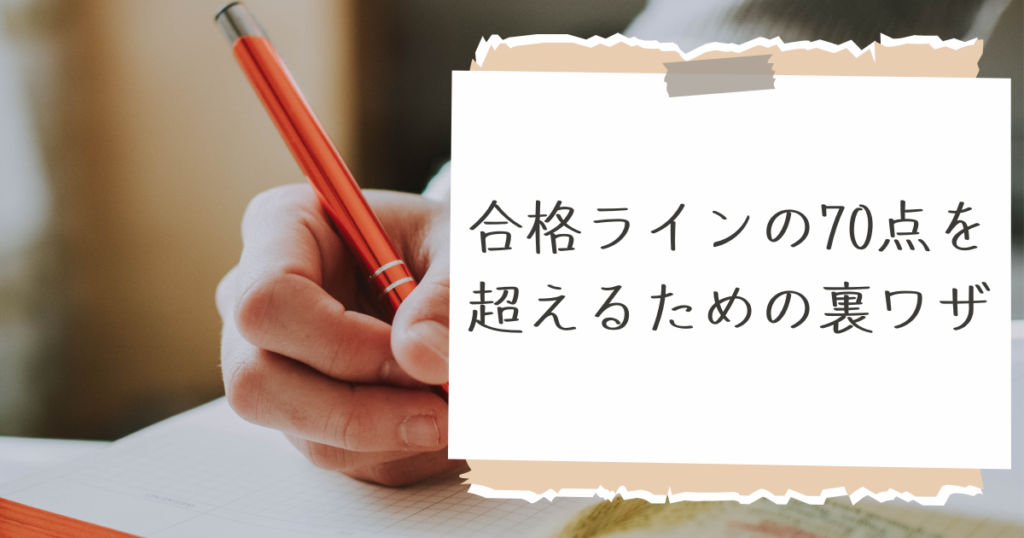
次に、試験直前で合格ラインの70点を超えるための裏ワザを3つご紹介します。
- 本試験では問題を順番通りに解かない
- 70点を目指すのではなく、一応100点を目指してみる
- ネット試験の無料体験プログラムを繰り返し受けてみる
簿記3級の試験は合格ラインの70点以上取れば必ず合格できる試験です。
極端なことを言えば、100点や90点などの高得点を取らずとも、70点以上の点数を取れれば簿記3級の資格を誰でも取得することが可能です。
前提条件としては、問題集の3周目を解き終わっている状態で最後の最後にこの合格ラインの70点を超えるための裏ワザ3選の紹介ということになります。
本試験では問題を順番通りに解かない
先ほど書いたように、簿記は第1問と第3問に大きく配点が割かれているため、一般的には下記の順番で解くのがセオリーと言えます。
第1問(45点) → 第3問(35点) → 第2問(20点)
理由としては、60分という時間制限の中で簿記3級の本試験を突破するためには、配点比率の大きい問題から解く方が合格に近づけるからです。
もし順番通りに解いて第2問で詰まってしまい、第3問に取り掛かれなかったら、たとえ第1問と第2問で満点を取ったとしても65点にしかならず不合格となってしまいます。
ですが、第1問、第3問、第2問の順で解いていけば、仮に第2問が時間切れとなってしまい、全く解けなかったとしても、第1問と第3問合わせて70点〜80点のラインを取れていれば合格できます。
本試験では必ず、配点比率の大きい第1問と第3問から解くようにしましょう。
70点を目指すのではなく、一応100点を目指してみる
簿記3級の試験は、大問が全部で3つ出題されます。
- 第1問 仕訳問題(45点)
- 第2問 勘定記入問題(20点)
- 第3問 決算整理問題(35点)
配点比率を見てもらえば分かる通り、仮に第2問が0点で第1問と第3問でもし満点近くの70点〜80点を取れたとしたら、それでも簿記3級は合格できます。
ただそれではあまりにバランスが悪いため、やはり最初は全範囲を満遍なくさらって、一応100点を目指す方が無難です。
「一応」と付けている理由としては、絶対にミスの無い完璧な解答を目指すという意味ではなく、全ての範囲を平均的に勉強をしてあわよくば100点に近い点数を目指せるといいよね、という意味で表記しています。
簿記は全ての単元がつながっていますので、第2問だけ捨てて他の範囲だけを勉強するということの方が逆に難しいです。
一応100点を目指してしっかりと全範囲を勉強しておけば、本試験で多少のケアレスミスをしても70点以上はキープできるでしょう。
本試験では問題を順番通りに解かない
先ほど書いたように、簿記は第1問と第3問に大きく配点が割かれているため、一般的には下記の順番で解くのがセオリーと言えます。
第1問(45点) → 第3問(35点) → 第2問(20点)
理由としては、60分という時間制限の中で簿記3級の本試験を突破するためには、配点比率の大きい問題から解く方が合格に近づけるからです。
もし順番通りに解いて第2問で詰まってしまい、第3問に取り掛かれなかったら、たとえ第1問と第2問で満点を取ったとしても65点にしかならず不合格となってしまいます。
ですが、第1問、第3問、第2問の順で解いていけば、仮に第2問が時間切れとなってしまい、全く解けなかったとしても、第1問と第3問合わせて70点〜80点のラインを取れていれば合格できます。
本試験では必ず、配点比率の大きい第1問と第3問から解くようにしましょう。
ネット試験の無料体験プログラムを繰り返し受けてみる
最後の裏ワザは、ネット試験の無料体験プログラムを繰り返し受けてみるという裏ワザです。
簿記3級の試験は、今まで通りの紙による統一試験とネット試験の2種類の試験方式がありますが、おすすめはネット試験の方です。
今はインターネット回線さえあれば、本試験と同じように自宅のパソコンを使ってネット試験の様式を再現し、過去問や模擬試験を受けることも可能。
本番さながらの環境で練習を繰り返すことで、試験当日もあまり気負わずに臨めるはずです。
なお、簿記の通信講座を展開する「ネットスクール」には、自宅で受けられるネット試験の無料体験プログラムがあるので、確認してみてくださいね。
テキストの著者が講師でわかりやすい
ネットスクール公式サイトをみるまた令和5年度から東京商工会議所では簿記3級と簿記2級の紙による統一試験の廃止を予定しており、将来的に他の商工会議所もこの流れに追随することは必至でしょう。
参考:東京商工会議所検定サイト (tokyo-cci.or.jp)
こういった今の時代の流れからも紙による統一試験のための対策ではなく、ネット試験の方の対策に比重をかけた方が良いです。
さらに今までの簿記試験の傾向として、紙による統一試験よりネット試験の方が合格率が高いという点もネット試験の方をおすすめする理由です。
現在、商工会議所が発表している直近第162回(2022.11.20実施)の簿記3級のデータを見てみると、統一試験の合格率は30.2%だったのに対し、同時期(2022年4月~2022年12月)のネット試験の合格率は41.5%となっています。
3級(統一試験)
| 回 | 受験者数(申込者数) | 実受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 162(2022.11.20) | 39,055名 | 32,422名 | 9,786名 | 30.2% |
| 161(2022.6.12) | 43,723名 | 36,654名 | 16,770名 | 45.8% |
| 160(2022.2.27) | 52,649名 | 44,218名 | 22,512名 | 50.9% |
| 159(2021.11.21) | 58,025名 | 49,095名 | 13,296名 | 27.1% |
3級(ネット試験)
| 期間 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年4月~2022年12月 | 143,989名 | 59,694名 | 41.50% |
| 2021年4月~2022年3月 | 206,149名 | 84,504名 | 41.00% |
商工会議所のホームページの文言には、「申込方法が異なるのみで、試験内容は同じです。」とありますが、直近の試験ではなぜか合格率に10%以上もの差が出ています。
さらに紙による統一試験は回によって合格率にかなりのバラツキがあり、あまりおすすめできません。
過去のデータを遡るとネット試験よりも合格率が高い回もありますが、極端に合格率の低い回もあります。
その点、ネット試験の方は合格率40%前後でおおむね安定しているのがわかります。
理由は明確ではありませんが、ネット試験に比べ紙による統一試験の場合は勘定科目の誤字・脱字、数字の桁数の間違いなどが発生しやすいのかもしれません。
その点、ネット試験の場合は勘定科目はプルダウン方式の選択式になっていたり、テンキーで数字をそのまま打ち込めば自動的にカンマも打ってくれたりするので、ケアレスミスによる間違いは少なくなると思います。
あとはパソコンに慣れている人であれば、手で書くスピードよりもキーボードを打つスピードの方がはやい人もいます。
そうすると、ネット試験でもし時間が余った場合には最後に検算をする時間を多めに取れるので、間違いに気づきやすいというのも合格率が高い理由なのかもしれません。
問題集を、無理なく最低3周まわすための裏ワザ
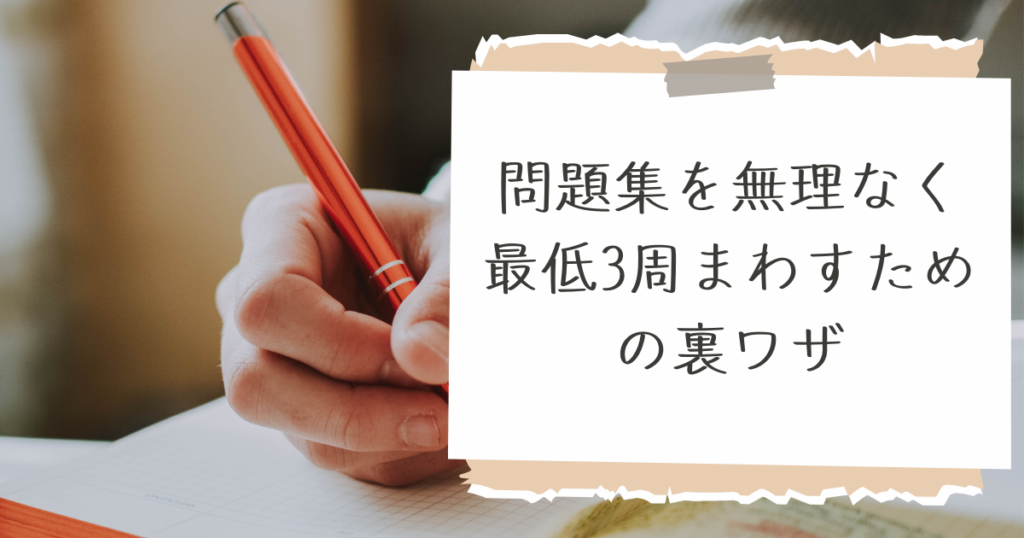
簿記の一般的な試験対策として、「最低でも同じ問題集を繰り返し3回は解きなさい」と言われたりします。
解き方や問題の傾向をつかむ上では、最低3回は問題集を解いたほうがいいのは事実です。
ですが、多くの受験生が問題集を1周解き終えるのにかなりの苦戦を強いられます。
なぜなら、教科書を一度読んですぐに簿記3級の問題集を解けるほど簿記の問題は簡単ではないうえに、簿記特有の癖みたいなものがあって解けるようになるまでは、ある程度の練習が必要だからです。
そのため、1周目でいきなり問題を解こうとしても恐らくほとんどの人は手が止まってしまいます。
かくいう自分自身もそうでした。
そこで、まずは簿記の問題に慣れるという作業が必須となり、反復して問題を解いて体に染み込ませていくための準備が必要となります。
ここでは体に染み込ませるという作業をスムーズにおこなうための裏ワザを3ステップで紹介します。
問題集の1周目は解答を見ながらすべての範囲を終わらす
最初のステップとしては、いきなり問題を解こうとしないことが肝です。
結論からお伝えすると、最初はいきなり答えをみながら解き方や内容、解説を理解することに努めましょう。
最初から問題を解こうとすると、なかなか手を動かせません。
ですが問題文を読んで解答や解説を理解するだけなら、スムーズに簿記3級の問題をどのように解けばいいのかを把握できます。
単発の仕訳の問題だけであれば、何度か読み込むことですぐに問題をとける人もいるかも知れません。
ですが、初学者にとって後半のP/LやB/Sを作成するための穴埋め問題などは、はじめに何をしていいのかがさっぱり分かりません。
実際に解答を読んで流れをつかんで、「ああ、こうやって解けばいいのかぁ」と気付くポイントが多々あるかと思います。
よく学校や塾の先生からは「まずはじめに自力で解いてみて、それでも分からなかったら解答や解説をみなさい」と言われることも多いと思います。
学校や塾の勉強はそれで対応できるかも知れませんが、簿記は今まで私たちが習ってきた科目とは異なり簿記特有の解き方があります。
最初は、その簿記特有の癖のようなものを掴むために解答をみて問題の解き方や解法の手順、流れを掴むことに重きを置くようにしましょう。
問題集の2周目は解答を見ずに、時間を気にせずに解く
2つ目のステップは、解答を見ずに問題を解くという作業をおこないます。
ここでのポイントは、解答に要する時間がどんなに長くなっても気にしないということです。
1周目でひと通り、簿記の問題の解き方の全体像のようなものは把握できているはずです。
ただ、実際に自力で問題を解こうとすると、なかなか手が動かなかったり、解法の手順が分からなかったりします。
この点こそが「簿記は手を動かして問題を解くのが定石」と世間一般的に言われている理由です。
この2周目以降の作業でようやく簿記の問題を解いているという実感を得られるかと思います。
そして、読んで理解しただけの1周目の時とは異なり、1問解くのに想像以上に時間がかかるということにも気づきます。
人によっては、大問を1つ解くだけで30分以上時間を費やすかもしれません。
しかし、実際の本試験では試験時間はわずか60分で、大問を3つ解き切る必要があります。
そう考えると、いかに素早く正しい回答を導き出せるかが重要になってきますが、まだ2周目でこのレベルに達しようと思ってはいけません。
この段階では、まずはどうやったら簿記独特の問題を解くことができるのかを、丁寧に頭と身体に覚えさせることの方が重要です。
本試験では時間制限がありますが、2周目に問題集を解く際は時間を気にせず着実に理解しながら解けるようにしていきましょう。
問題集の3周目は時間を計って本番と同じように解く
3つ目のステップは、いよいよ本番と同じようにして時間を計って解くという作業です。
2周目までに1回はすべての問題を手を動かして解いているはずなので、本試験と同じように時間を計って解いてみれば本番の感覚が掴めるかと思います。
実際に時間を計って解くことで、本試験ではどれくらいのペースで問題を解いていかなければならないかが分かるはずです。
スムーズに解ければ最後に多少の検算をする余裕があるかと思いますが、どこかの問題でつまずいてしまうと、解答時間はかなりギリギリになってしまうでしょう。
こればかりは、実際に本試験と同じように外の情報を全てシャットアウトして、タイマーなどで計ってやってみるしかありません。
家の中では家族の会話やテレビの音などに邪魔されて、どうしても集中できない人は図書館や町の自習室などに行って、絶対に誰にも邪魔されない環境で作業するのも良いでしょう。
最初は制限時間内に解くことは難しいかもしれません。
ですが、何回も何回も繰り返し練習問題や模擬試験の問題を解いていくことで仕訳をするスピードも上がり、勘定科目を集めて整理することにも慣れてくるはずです。
簿記は知識や暗記の作業も多少はありますが、その半分は技術の部分も大きいと言われています。
ひたすら問題を解いていくことで確実に問題を解くスピードはあがりますし、記憶もしっかりと定着していきます。
色々な問題集に手を出さずに、同じ問題集を3周目まで解き切ることが何よりも大事です。
簿記3級の裏ワザは特別な技術は不要で知っているか知らないかだけ
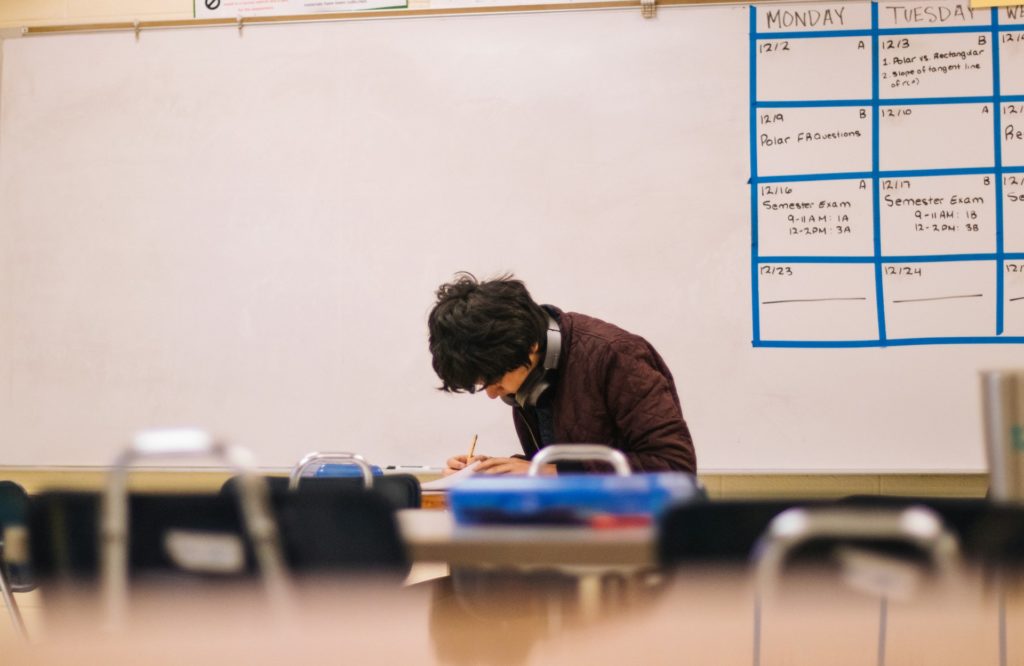
いままで見てきたように簿記3級の裏ワザはほぼ全て知っているか知らないか、の違いだけです。
知っていれば簿記3級の対策を効率よくおこなうことができますし、知らなければ多くの時間を割かなければなりません。
もしここでご紹介した裏ワザをいっぺんに利用するのが難しければ、できそうな裏ワザから徐々に取り入れていくと良いでしょう。
これらの裏ワザをうまく活用していけば、本試験直前になって「勉強時間が足りない!」ということにはなりにくいですし、自信を持って本試験に臨むことができるはずです。
効率よく試験対策をおこなって、簿記3級の資格取得を目指していきましょう。
なお、簿記3級をとにかく効率的に学ぶなら、合格範囲に絞って勉強するのが一番。
簿記の通信講座クレアールは、「非常識合格法」という合格に必要なことだけをピンポイントで学べるカリキュラムが特徴的です。
一度、無料で資料請求をして教材内容をチラ見してみてくださいね。
無料の資料請求で割引あり
クレアール簿記講座の資料を請求する