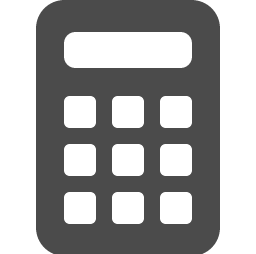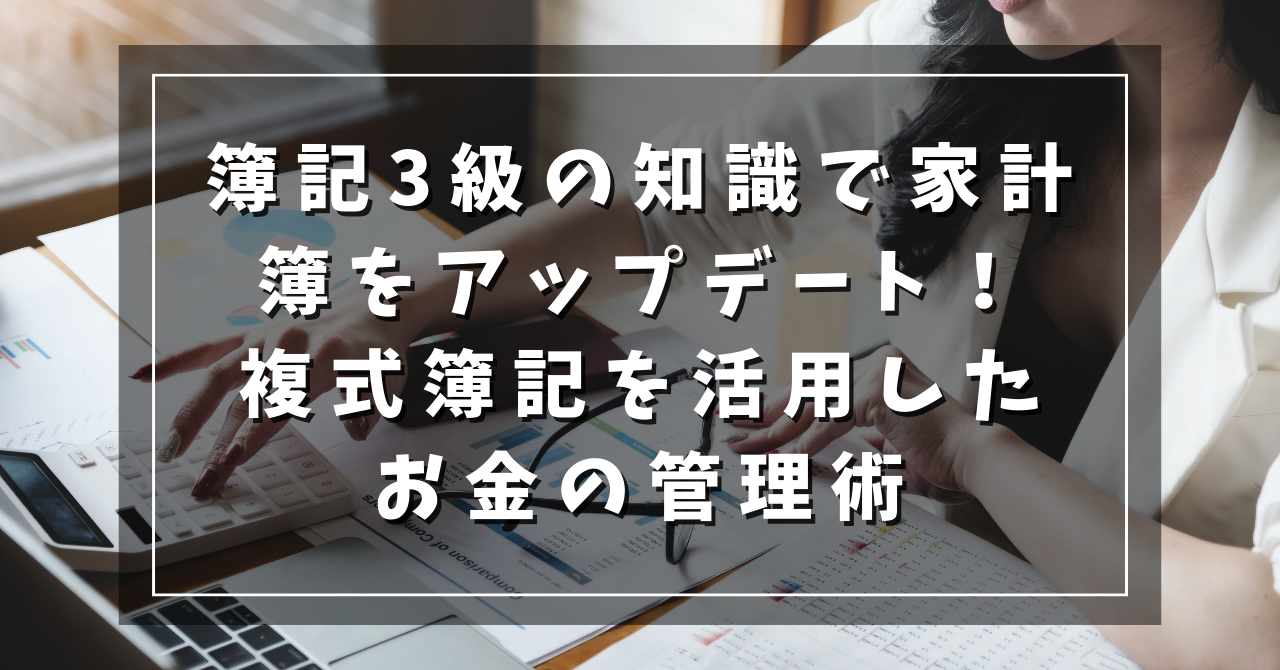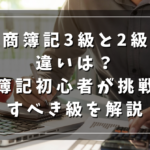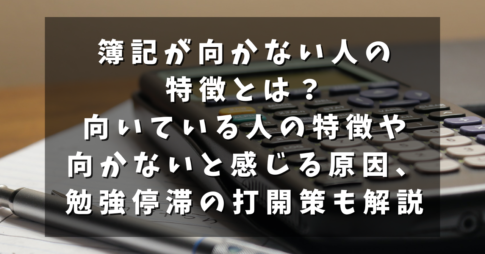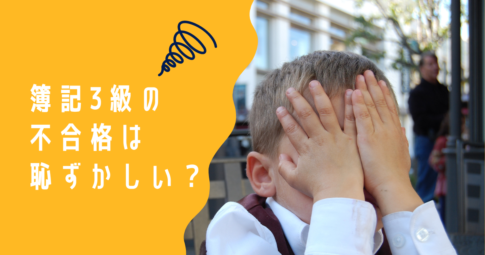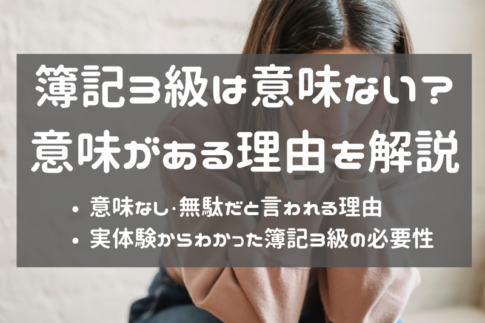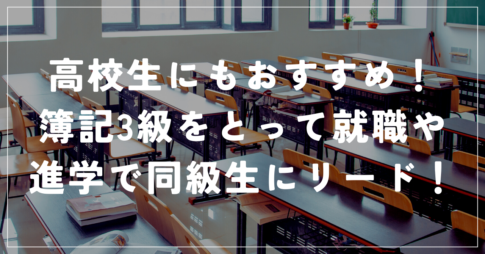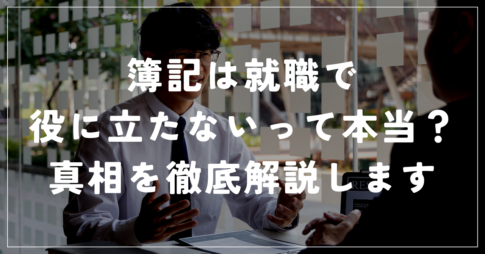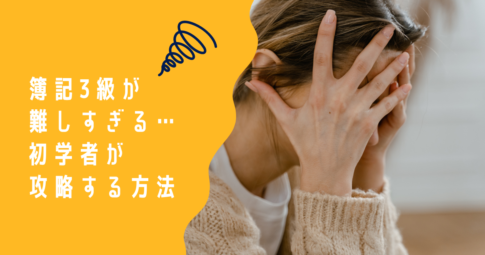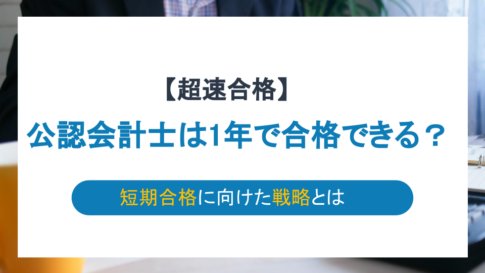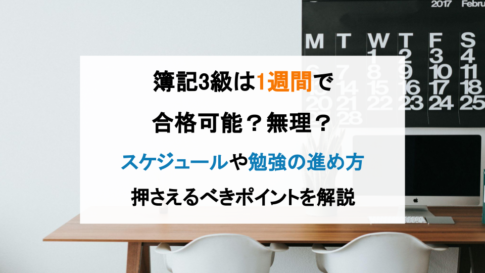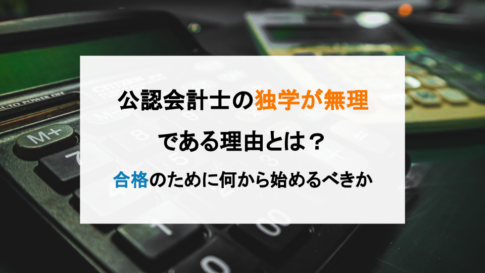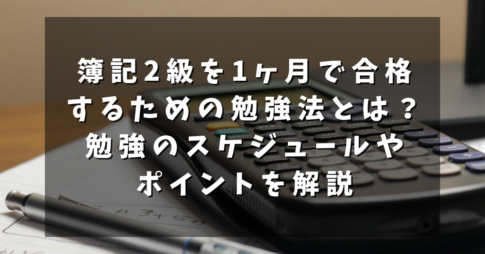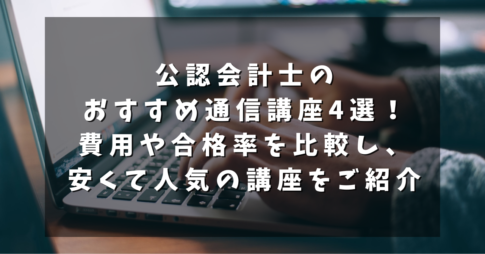簿記3級の試験では、複式簿記という技術を使って会社の財政状態や経営成績を把握するための方法を勉強をします。
この複式簿記を理解できるようになると、簿記の考え方が身につき、家計の大幅な改善にも繋がるでしょう。
通常、一般的な家計簿は簿記で使用する複式簿記の技術を使わずに、もっとシンプルな方法で記入をしていきます。
ですが、せっかく家計簿をつけても、なかなか家計の改善に繋がらなかったり、カテゴリーごとの支出費目を分けるのが難しかったりします。
今回の記事を読めば、そんな悩みはすぐに解決できるでしょう。
ぜひ、複式簿記を活用した家計簿の使い方を知って、今よりも効果的に家計の改善を図っていきましょう。
なお、簿記3級をこれから学びたいという方、過去に学んだけど記憶に少し自信がないという方は、簿記3級のテキストや動画が無料で見られるCPAの資料請求がおすすめです。
- 簿記3級の全12回の動画講義(全12時間)
- 簿記3級のテキスト(PDFで全400ページ)
- 簿記3級の解説付き問題集(PDFで全300ページ)
これらが無料でもらえるサービスは、他には見たことがありません。
いつまで公開しているか分かりませんので、今のうちに下記から資料請求をしてテキストをゲットしておくことをオススメします。
目次
簿記3級講座の比較表
| CPA会計学院 | クレアール | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 3,850円 | |
| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |
| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限で可能 |
| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | スマホで倍速視聴 | 合格範囲の効率学習 |
| 実績 | × | 年間合格1,000人超 | × |
| 公式 | 無料の資料請求 | 無料の資料請求 |
家計簿によって収支を把握する

まずは、一般家庭で使用されている家計簿について簡単に再確認していきましょう。
家計簿とは何か
家計簿とは、家庭での収支を記録する簡単な帳簿のことです。
家計簿をつけることによって、今までどんぶり勘定で何となく把握していた収支を数字で正確に確認することが可能。
もう少し細かく書くと、一般的な家計簿は「収入ー支出」で記録していく「単式簿記」と呼ばれる方法で記載されます。
単式簿記についての細かい説明は後述しますが、簡単に言うと、1つの取引について1つの記録をする記帳方法のことを言います。
なぜ家計簿をつける必要があるのか
家計簿は収支状況を客観的に把握して、支出が多いものや無駄な支出を見つけることで、家計の改善を図るために記録します。
無駄な支出を抑えることで、節約につなげたり、貯金をしたり、将来の資産形成に役立ったりすることもあるでしょう。
家計簿をつけることで、計画的に収支のバランスを見直せます。
家計簿のつけ方の基本的な手順
一般的な家計簿のつけ方は以下の通りです。
- 収入と支出の項目を洗い出す
- 日々の収入と支出を記録する
- 残高を確認して、収支バランスを整える
月末時点で黒字だったらその分を貯金や投資に回し、逆に赤字だったら貯金から補填して、翌月以降の支出を見直すという方法が一般的かと思います。
複式簿記の考え方を取り入れた家計簿を作成する

ここまで一般的な家計簿の記帳方法を見てきました。
次は、簿記3級の内容をベースにした「複式簿記」という概念を用いた家計簿について見ていきましょう。
複式簿記とは
複式簿記は取引の動きを見るために、原因と結果を記述していく記帳方法のこと。
ちなみに、帳簿の左側を「借方(かりかた)」、右側を「貸方(かしかた)」と呼び、2つ以上の項目を使って記録する記帳方法となります。
普通の家計簿と複式簿記を活用した家計簿の違い
先ほども少し触れましたが、お小遣い帳のような普通の家計簿は「単式簿記」という方法で記帳されることを前提としています。
そのため、街の文房具屋さんで売っている一般的な家計簿は、この単式簿記をベースにレイアウトが組まれています。
文章だけだとイメージしづらいと思いますので、具体例を交えてそれぞれの記帳方法の違いについても見ていきましょう。
5月1日に電気代を現金で支払った場合
- 単式簿記 ⇒ 5月1日 電気代 8,000円(支出に記入)
- 複式簿記 ⇒ 5月1日 電気代 8,000円 現金 8,000円
単式簿記では項目が1つなのに対して、複式簿記では項目が「電気代」と「現金」の2つの項目になっています。
このように、電気代と現金を借方と貸方に分けて記入する方法のことを「仕訳(しわけ)」と呼んでいます。
仕訳については簿記3級試験の中では、最重要論点の1つですが、ここではこんな風に書けばいいんだな、ということだけ把握しておけばOK。
簿記3級ではこんなことを勉強するんだな、ということだけ覚えておいてください。
5月25日に現金で12,000円の売上収入があった場合
- 単式簿記 ⇒ 5月25日 現金 12,000円(収入に記入)
- 複式簿記 ⇒ 5月25日 現金 12,000円 売上 12,000円
ここでも、単式簿記では項目が1つなのに対して、複式簿記では項目が「現金」と「売上」の2つの項目が対になっています。
売上のイメージとしては、メルカリなどで中古品が12,000円で売れたことを想像すれば分かりやすいでしょう。
こちらも仕訳によって、現金と売上の項目が借方と貸方に分けて記入されます。
ここで、先ほどと現金の位置が右と左で違っている理由について少しだけ触れておきましょう。
現金は「資産」というカテゴリーに属し、資産が増えたときは借方(左側)に記入し、資産が減ったときは貸方(右側)に記入するという簿記のルールがあります。
そのため、電気代を支払ったとき(資産が減ったとき)は現金が借方に、売上収入があったとき(資産が増えたとき)は貸方に記入されます。
単式簿記と複式簿記の特徴
単式簿記と複式簿記の特徴について整理すると、以下のようになります。
- 単式簿記は記録するのが容易である反面、現金の増減を記帳するだけで、お金の流れや出所が把握しづらい
- 複式簿記は、簿記の概念やルールを把握していないと記録をするのが難しい反面、お金の流れや出所を把握しやすい
この複式簿記の知識と技術を習得するためには、簿記3級の内容をしっかりと学ぶ必要があります。
複式簿記を取り入れた家計簿の3つの利点・メリット

複式簿記のルールをしっかりと理解して家計簿を記入できるようになると、今よりもお金の流れをしっかりと把握できますし、将来に向けての資産形成も一層スムーズにおこなえます。
そこで、この複式簿記のメリットについてもう少し具体的に見ていきましょう。
利点1:収支のバランスがわかりやすい
複式簿記を用いた家計簿では、収入と支出がそれぞれ明確に分かれているため、収支のバランスを把握するのが容易となります。
たとえば、食費、家賃、通信費、交際費、医療費などの項目をカテゴリーごとに記録し、同じカテゴリーを集計することで支出が多い項目をピックアップすることも可能。
もし、毎月の収支のバランスがプラスであれば「収入>支出」となるため、余剰資金を貯金等にまわせます。
逆に、毎月の収支のバランスがマイナスであれば、「収入<支出」となるため、貯金を切り崩したり、今後の生活に支障が出たりすることもあるでしょう。
このように、項目ごとの収支のバランスが明確になることで、家計の見直しや今後の生活設計の改善につなげられます。
利点2:支出の詳細がわかる
さきほども少し触れましたが、複式簿記を用いた家計簿では、支出項目を食費、家賃、通信費、交際費、医療費などに分けておくのが一般的です。
たとえば、食費を例にとって説明をしてみると、次のように書くことも可能です。
- 食費(食料品)
- 食費(朝食)
- 食費(昼食)
- 食費(夕食)
もう1つ例を挙げてみます。
- 通信費(スマホ通信費)
- 通信費(プロバイダー料金)
- 通信費(固定電話料金)
通常の家計簿では、カテゴリーごとに集計することはあまり無いかも知れません。
ですが、このようにカテゴリーごとに分けておくと毎月どんな支出項目に、どれくらいの出費が掛かっているのかをすぐに把握できます。
たとえば、家計全体を見たときに通信費が家計をひっ迫している場合は、格安スマホに切り替えるなどの選択をしてバランスを整えるのも良いでしょう。
利点3:将来の計画に役立つ
複式簿記を用いた家計簿では毎月の収支を取りまとめたあとに、資産と負債の変動を記録します。
この作業をすることによって、家計の本当の資産を一目で把握できます。
たとえば、手元に50万円の現金があって、借金が45万円あった場合の例を挙げてみましょう。
資産50万円-負債45万円=本当の資産5万円
という計算となり、手元に現金が50万あったとしても、家計の本当の資産は5万円しかありません。
この「資産-負債」で計算された本当の資産のことを「純資産」と呼んでいます。
純資産がプラスになっていれば家計は比較的健全と言えますが、もし純資産がマイナスとなっている場合は、早急に家計の改善が必要です。
このように、家計の本当の資産である純資産が目に見える形になることで、将来の計画をより具体的に立てられるでしょう。
複式簿記を家計簿に取り入れるための具体的な方法

ここまで、複式簿記を取り入れた家計簿の利点・メリットについて書いてきました。
ですが、実際の数字・項目等があった方が分かりやすいと思いますので、このあと具体的に見ていきます。
【事前準備】家計の資産や負債を洗い出す
まずは家計全体の資産と負債を洗い出す作業をおこないましょう。
現時点の資産と負債を把握しておくことで、どのように目標を立てて家計を改善していくかが容易になります。
資産と負債については、以下のようなものが挙げられます。
【資産】
- 現金
- 株式
- 不動産(持ち家など)
- 投資信託
- 株式
- 車両(自家用車など)
【負債】
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- クレジットの残高
- 奨学金
資産-負債=純資産となり、以下の表のようになります。
この表のように、資産・負債・純資産の財政状態を表したものを簿記の専門用語で、「貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)」と呼んでいます。
<貸借対照表>
| 資産 現金、株式、不動産、投資信託、車両 | 負債 住宅ローン、自動車ローン、クレジットの残高、奨学金 |
| 純資産 (家計の本当の資産) |
どの項目が「資産」で、どの項目が「負債」なのか、貸借対照表をみると一目瞭然ですね。
損益計算書を使って毎月の収支を把握する
貸借対照表で現時点の家計の資産・負債・純資産を把握できたら、次は毎月の収支を家計簿に付けていきます。
もちろん、ここでも複式簿記の概念を利用して収支を記録していきますね。
収入と支出については、以下のようなものが挙げられます。
【収入】
- 給与収入
- 配当金収入
- 利子収入
- その他の収入
【支出】
- 住居費
- 光熱水費
- 食費
- 医療費
- 交通費
- 通信費
- エンタメ費
- その他の支出
こちらも、貸借対照表と同じように表にまとめてみましょう。
ある期間内の収入と支出を比較して、その期間の利益や損失を計算する書類のことを、複式簿記では「損益計算書(そんえきけいさんしょ)」と呼んでいます。
<損益計算書>
| 支出(費用) 住居費、光熱水費、食費、医療費、交通費、通信費、エンタメ費その他の支出 | 収入(収益) 給与収入、配当金収入、利子収入、その他の収入 |
当期純利益 (収支がマイナスの場合は当期純損失) |
このように、カテゴリーごとに収入と支出を分けて記録していくことで、毎月の収支の把握が容易になります。
収益ー費用=収支が「プラス」または「マイナス」
ちなみに、損益計算書において、収支がプラスの場合は「当期純利益」、収支がマイナスの場合は「当期純損失」という呼び方をします。
複式簿記を用いた家計簿では、この損益計算書を使って作成すると収支のバランスが把握しやすくなります。
収支を把握したら、貸借対照表に反映させる
1ヶ月の収支を記録したら収入と支出の差額を全て計算して、月末時点の収支がプラスだったのか、マイナスだったのかを確認しましょう。
この損益計算書で計算した収支がプラスだったら貸借対照表の「資産」のカテゴリーへ、逆にマイナスだったら「負債」のカテゴリーへ、その数字を反映させます。
作成する順番としては以下のようになります。
- 【ステップ1】現時点で資産・負債・純資産を洗い出し、貸借対照表を作成する
- 【ステップ2】毎月の収支を計算して、損益計算書を作成する
- 【ステップ3】当期純利益 or 当期純損失を貸借対照表に反映させる
複式簿記を用いた家計簿を活用するためには、この【ステップ1】~【ステップ3】までの手順を毎月おこなっていけばOKです。
損益計算書と貸借対照表を使った具体的な記入方法
それでは、貸借対照表や損益計算書に、実際に数字を入れて具体的に記入をおこなっていきましょう。
ここでは、損益計算書の収支がプラスだった場合のパターンを考えてみます。
【ステップ1】現時点で資産・負債・純資産を洗い出し、貸借対照表を作成する
まずは、先ほどと同じように現時点の純資産を把握しておきます。
資産100万円-負債80万円=純資産20万円
資産と負債の差額を計算すると、当初の純資産は20万円であったことが分かります。
<貸借対照表>
資産 100万円 | 負債 80万円 |
| 純資産 20万円 |
【ステップ2】毎月の収支を計算して、損益計算書を作成する
次に毎月の収支を把握していきましょう。
収入30万円-支出20万円=当期純利益10万円
この月は、収入と支出の差額が20万円となっており、当期純利益は10万円であったことが分かります。
<損益計算書>
| 支出(費用) 20万円 | 収入(収益) 30万円 |
| 当期純利益 10万円 |
【ステップ3】当期純利益 or 当期純損失を貸借対照表に反映させる
最後に【ステップ2】で算出した当期純利益の10万円を、貸借対照表に反映させましょう。
当期純利益はそのまま、資産に繰り入れれば良いので元々あった100万円に10万円をプラスします。
ステップ1と同様に再度、資産と負債の差額から純資産を計算してみましょう。
資産110万円-負債80万円=純資産30万円
このような結果となり、【ステップ1】の20万円の時点よりも、純資産が10万円アップして30万円になりました。
この【ステップ1】から【ステップ3】までの作業を毎月おこなうことで、家計の本当の資産をその都度把握できるのが、複式簿記を利用した家計簿の最大の特徴と言えます。
<貸借対照表>
資産 110万円 | 負債 80万円 |
| 純資産 30万円 |
簿記3級を学んで、複式簿記の概念を家計簿に取り入れてみよう

習得するのに少し時間はかかりますが、複式簿記を活用した家計簿を活用できるようになれば、今まで見えていなかった家計の本当の純資産を把握できるようになるでしょう。
ポイントは、資産と負債の差額から、今現在の純資産がどれくらいあるのかを認識することにあります。
この、純資産が常にプラスになるよう家計簿をつけておけば、毎月の家計のやりくりで頭を悩ませる必要はありません。
また、純資産を把握することで大きな借金を抱えたり、クレジットカードを使いすぎたりするリスクも回避できます。
ぜひ簿記3級を学んで、複式簿記を活用した家計簿を使いこなせるようになりましょう!
簿記3級講座の比較表
| CPA会計学院 | クレアール | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 3,850円 | |
| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |
| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限で可能 |
| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | スマホで倍速視聴 | 合格範囲の効率学習 |
| 実績 | × | 年間合格1,000人超 | × |
| 公式 | 無料の資料請求 | 無料の資料請求 |