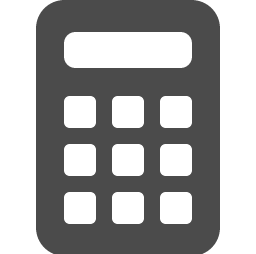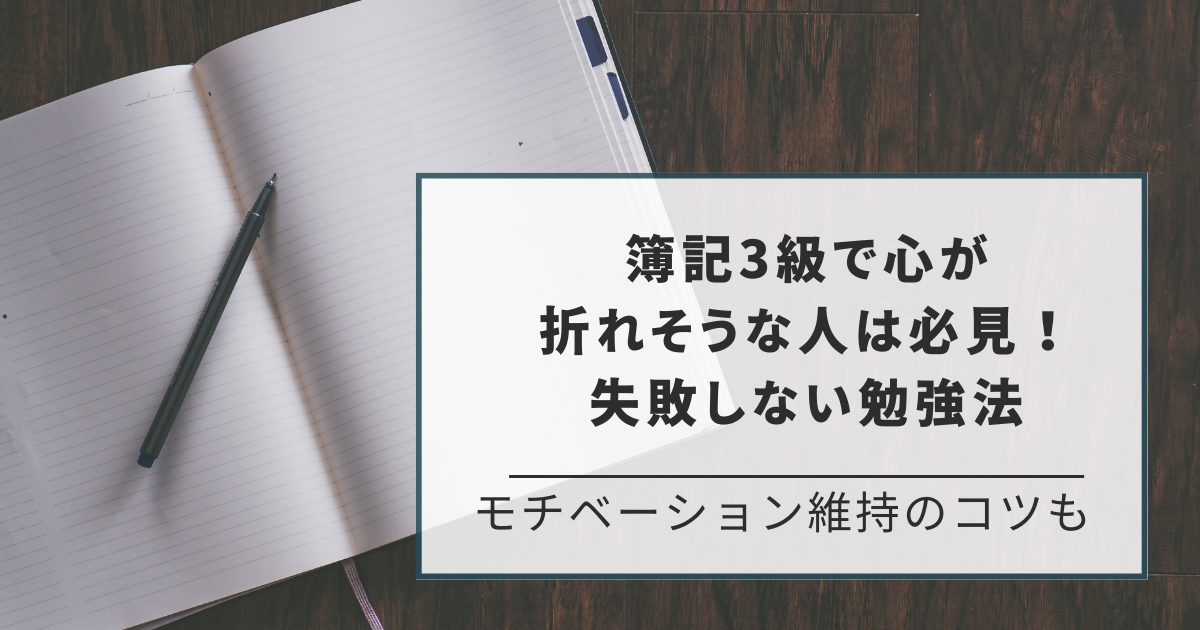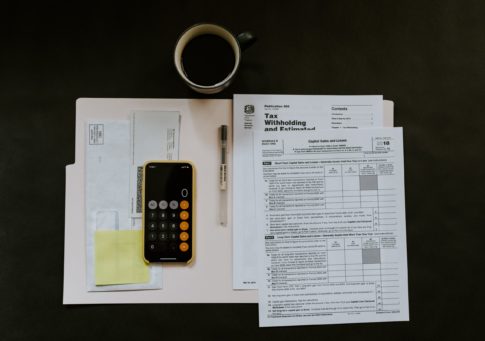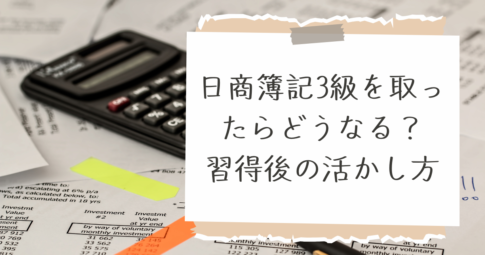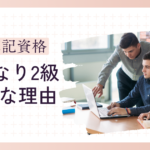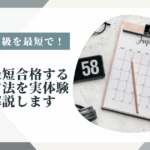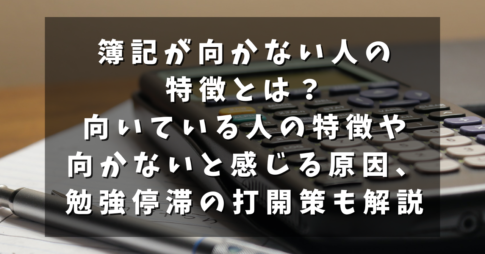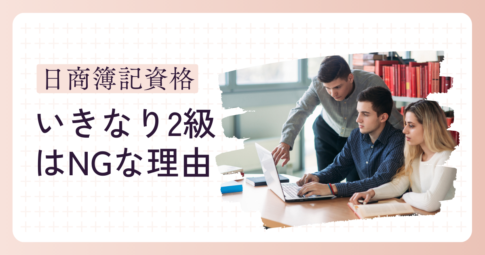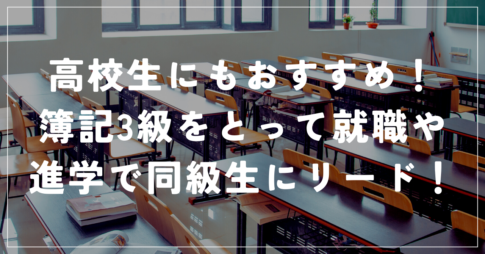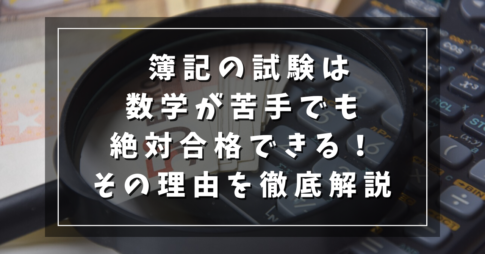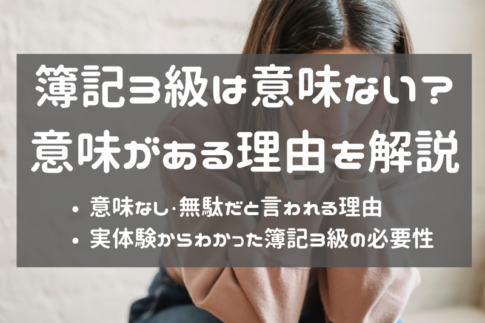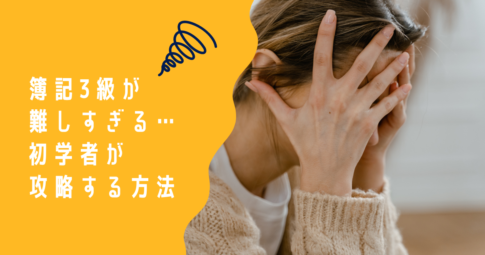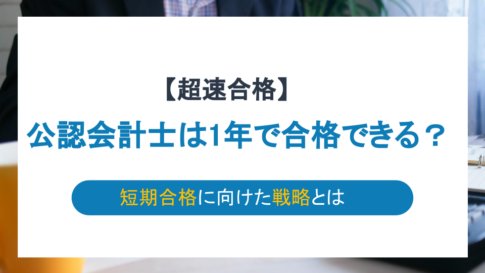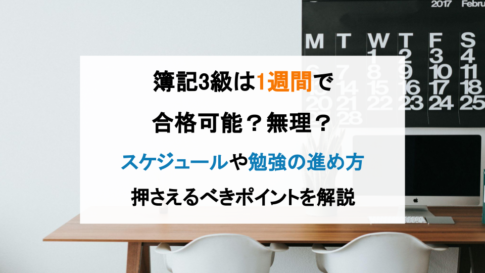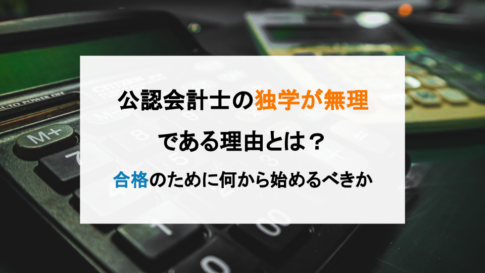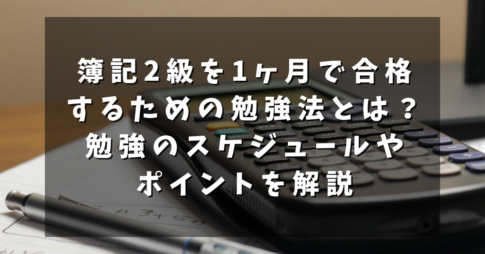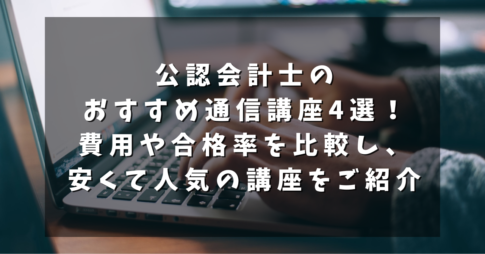簿記は今まで学校や塾で習ってきた国語や数学のような学問と異なり、独特の癖やルールがあります。
そのため、一人で勉強を続けていると時々心が折れそうになる瞬間が訪れることがあります。
「なんでこの仕訳になるんだろう?」、「解説のここの説明がよく分からない」、「専門的な用語が多すぎて何を言っているのか分からない」、「どうしても計算の結果が合わない」など、つまずきやすいポイントが多々あります。
また、一度簿記3級の勉強をしたものの、どうしてもポイントをつかみ切れずに不合格になってしまった人もいるでしょう。
簿記3級の内容は、2級や1級を目指すことを踏まえても、とても大事な要素がギッシリと詰まった重要な論点が盛り沢山です。
最初の段階でつまずかないために、ここでは適切な勉強法やモチベーションを維持するコツなどを具体的に解説していきます。
目次
簿記3級講座の比較表
| CPA会計学院 | クレアール | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 3,850円 | |
| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |
| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限で可能 |
| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | スマホで倍速視聴 | 合格範囲の効率学習 |
| 実績 | × | 年間合格1,000人超 | × |
| 公式 | 無料の資料請求 | 無料の資料請求 |
簿記3級で、心が折れそうになる主な原因5選

簿記3級の勉強で心が折れそうになる原因は数多くあると思いますが、ここでは以下の5つの原因について最初に掘り下げていきます。
- 他の資格試験と同様に独学で乗り切ろうとする
- 見たことも聞いたこともない用語だらけ
- 資産・負債・純資産・収益・費用と勘定科目の関係が分からない
- 最初は簿記全体の流れをつかむのが難しい
- 大問を1つ解くだけで恐ろしいほど時間がかかる
自分自身が初めて簿記の世界へ足を踏み入れた時につまずいたポイントも、この5つが主な原因でした。
これから勉強を始める人はこの記事を参考に、効率よく勉強を進めて頂けたらと思います。
後半の記事では、これら5つの原因に対処するためのそれぞれの勉強法もご紹介します。
他の資格試験と同様に独学で乗り切ろうとする
今まで簿記以外の資格試験で合格を勝ち取ってきた人の中には、独学で勉強して試験を通過した人もいるかと思います。
たとえば、簿記3級と比較されることの多いFP(ファイナンシャルプランナー)3級の試験は合格率も簿記3級よりも高く、独学でも充分乗り切れます。
参考:FP(ファイナンシャルプランナー)3級は独学合格可能か? (foresight.jp)
そのため、過去にそのような成功体験がある人ほど独学で乗り切ろうとしてしまいます。
そうすると、わざわざ人に説明をして貰わなくても大丈夫という過信が働き、教科書やテキストの勉強のみで乗り切ろうとしてしまいます。
費用もテキストと問題集のお金くらいしか掛かりませんので、自分も最初はこの方法で乗り切ろうとしましたが見事に失敗しました。
簿記の世界には独特の癖やルールがあり、テキストを読んだだけではなぜそのような結果になるのか解説を読んでも全く分かりませんでした。
当然そんな状態で問題集を解いてみても、全く手が動きませんし、解説を読んでも何をやっているのか把握することもできません。
簿記の世界の癖やルールをつかむためにも、最初から独学で勉強をスタートするのは避けた方が無難です。
見たことも聞いたこともない用語だらけ
簿記の勉強を始めると、今まで日常生活では見たことも聞いたことも無いような用語が沢山出てきます。
「売掛金」、「買掛金」、「受取地代」、「租税公課」、「貸倒引当金」、「減価償却費」、「貸倒損失」、「繰越利益剰余金」など、最初はそれらの用語やその意味を覚えるだけでも、精一杯。
経理職に就いている人以外はまずこれらの用語を覚え始めることからスタートしなければなりません。
特に仕訳で使う主要な「勘定科目」については必ず覚えておかなければなりません。
勘定科目はお金の流れを示す見出しのようなもので、簿記3級の試験で出てくるものだけでも、ざっと100種類ほどあります。
参考:簿記3級の勘定科目の覚え方を伝授!勘定科目がわかれば仕訳問題も怖くない! | 簿記のCPAラーニング (cpa-learning.com)
そのため、試験直前は自分も勘定科目の表を持ち歩いたり、壁に貼ったりして、記憶に定着させていました。
勉強をはじめた段階では、これらの用語やその意味について何も知らない状態です。
用語の意味が分からなければ問題で何を問われているのか理解できないので、最初にここの段階で心が折れかけます。
資産・負債・純資産・収益・費用と勘定科目の関係が分からない
簿記の世界には、資産・負債・純資産・収益・費用という5つのカテゴリーがあり、これらの要素に属するものについては、会計上のルールで決まっています。
実はこの、資産・負債・純資産・収益・費用は各勘定科目と対応しています。
先ほどあげた勘定科目を例に挙げると、「売掛金」は資産、「買掛金」は負債、「繰越利益剰余金」は純資産、「受取地代」は収益、「減価償却費」は費用、といった具合です。
この5つのカテゴリーに対応する勘定科目は、そのルールに基づいてどこのカテゴリーになるのかを確認しながら覚えていかなければなりません。
もし間違って覚えてしまうと、各帳簿を作成するための仕訳をきちんとおこなうことができません。
そうすると、損益計算書や貸借対照表を作成する問題などが解けなくなってしまいます。
この点が、簿記が普通の暗記科目とは異なると言われるゆえんでもあり、独特の癖やルールがあると言われている理由でもあります。
最初は簿記全体の流れをつかむのが難しい
簿記3級の勉強をしばらく続けていると、今自分が一体何をやっているのか分からなくなる瞬間があります。
その原因は、簿記全体の流れを把握していない状態のまま、目の前の問題を解いていることにあります。
基本的な簿記全体の流れは以下の通りです。
- 取引の発生
- 仕訳をする
- 総勘定元帳に転記をする
- 試算表をつくる
- 決算整理
- 損益計算書と貸借対照表の作成
- 帳簿を締め切る
※7番までいったら、再び1番に戻る
簿記3級の問題を解くときは自分が1〜7番のどこの作業をしているのか、常に把握しながら解いていかないと迷子状態になってしまいます。
大問を1つ解くだけで恐ろしいほど時間がかかる
勘定科目や簿記全体の流れもつかんで「あとは試験問題を解くだけ!」という段階でつまずくポイントが、解答にもの凄く時間が掛かるという事実です。
過去問や練習問題で、精算表、試算表、損益計算書、貸借対照表と呼ばれる帳簿を作成する問題があるのですが、最初は中々スムーズに解くことができません。
というのも、簿記の世界では左右の数字が必ず一致するというルールがあるのですが、中々その数字が一致しないことが多いのです。
原因は様々ですが、途中の仕訳を間違えていたり、転記の際に別のところに記載していたり、電卓の数字を打ち間違えていたり。
これら様々なポイントをミスなく処理していかないと、数字が一致することは絶対にあり得ません。
そのため、練習問題を1つこなすだけでも最初は恐ろしいほど時間が掛かります。
人によっては大問を1問解くだけで1時間ほど掛かることもあるため、一体あとどれくらいの勉強時間が必要なんだろう…と絶望することになります。
簿記3級合格のための失敗しない勉強方法5選

ここまで簿記3級で、心が折れそうになる主な原因を見てきました。
今度はそれぞれの原因に対して、失敗しない勉強方法を解説します。
- 通信講座や資格試験予備校の講義を利用する
- 何度も問題を解いて専門用語を日常用語レベルまで落とし込む
- 暗記すべき所と、理解すべきところのポイントを押さえる
- 簿記全体の流れを、常に把握しながら問題を解く
- 最初は時間が掛かってもいいので、時間を計って問題を解いてみる
さっそく順番に見ていきましょう。
通信講座や資格試験予備校の講義を利用する
簿記3級の勉強を始めるならテキストではなく、やはり通信講座や資格試験予備校の講義を利用するのが最も効果的です。
カリキュラムもきちんと体系的に組まれていますし、説明も分かりやすいので、すんなりと内容が頭に入ってくるでしょう。
特に、難しい専門用語や簿記独特の癖やルールについて、初学者でも分かるようかみ砕いて説明をしてもらえるのは講義ならではのメリットです。
動画を見たり、実際の講義を聞いたりした後に、テキストを読むと理解が断然早くなります。
さらに問題集を解いた後に、復習がてら再び講義を聞けば、記憶にもしっかりと定着するでしょう。
暗記ではなくきちんと理解して勉強を進めれば、少し内容を忘れたとしても同じような問題に触れればすぐに思い出すこともできます。
もし分からない部分があっても、メールやチャットですぐに質問できるような体制が整っているのも魅力的です。
少し費用はかかるかもしれませんが、自分への投資だと思って最初は通信講座や資格試験予備校の講義を利用することをオススメします。
何度も問題を解いて専門用語を日常用語レベルまで落とし込む
簿記3級を勉強し始めた当初は専門的な用語の羅列ばかりで、中々学習をスムーズに進められません。
一度覚えた用語でも、しばらく触れてないと忘れてしまったり、難しい用語が中々覚えられなかったり。
たとえば、簿記3級の勘定科目の中で「租税公課」という勘定科目が出てくるのですが、自分はこの意味について中々覚えられませんでした。
ちなみに「租税公課」は費用の勘定科目で、租税と公課それぞれの意味は以下のようになっています。
- 租税 ⇒ 国や地方自治体に納付する国税や地方税などの税金
- 公課 ⇒ 行政サービスにかかる費用や手数料・罰金など公的な課金
特に後半の公課についての意味が覚えづらく、いつも何だっけ?となっていました。
このように、日常生活であまり使わないような用語は、出題されたらすぐに反復して覚えるようにしていきましょう。
きちんと意味とセットで用語を覚えるためには、何度も何度も問題を解きながら専門用語を日常用語で使用できるくらいまで定着させる必要があります。
そこまで覚え込めば、問題を解くときにこれってどんな意味だっけ?という初歩の段階のつまずきポイントはクリアできます。
暗記すべき所と、理解すべき所のポイントを押さえる
簿記には暗記で対応しなければならない部分と、理解で対応しなければならない部分があるので、この点についても要注意です。
勘定科目やその意味については暗記で対応すれば誰でも覚えられますが、その勘定科目が仕訳の際にどんな役割を果たすのかはきちんと理解して対応しなければなりません。
たとえば、先ほど挙げた「租税公課」の意味についてはそのまま覚えればOKです。
ただし、租税公課が費用の勘定科目であること、その性質によって仕訳をする際にどんな役割を果たすのかは「暗記」ではなく「理解」で対応しなければいけません。
租税公課は言葉を変えて、「印紙代」、「店舗や建物の固定資産税」、「自動車税」などの用語で出題されることもあります。
もし、これらの費用が租税公課であることをきちんと把握しておけば、費用の勘定科目としてすぐに仕訳をすることが可能です。
仮に全部暗記で対応していたら、印紙代も、店舗や建物の固定資産税も、自動車税も習ってない!ということにもなりかねません。
このように少しひねった問題が出題されたとしても、暗記すべき所と理解すべき所のポイントを押さえていれば、すぐに対応可能です。
簿記全体の流れを、常に把握しながら問題を解く
簿記の問題を解くときは、常に簿記全体の流れを把握したうえで問題を解くことが重要です。
もう一度、簿記全体の取引についておさらいしてみます。
- 取引の発生
- 仕訳をする
- 総勘定元帳に転記をする
- 試算表をつくる
- 決算整理
- 損益計算書と貸借対照表の作成
- 帳簿を締め切る
※7番までいったら、再び1番に戻る
簿記の練習問題を解いていると、単発で仕訳をする問題が割と多く出題されます。
ただ仕訳をするだけなら、慣れてくればすぐにできます。
ただし、その仕訳自体が1〜7番のどこの部分の作業なのかを把握しながら解くというのが重要です。
なぜなら、簿記3級の試験では決算での修正手続き、推定型の問題など、あらゆる角度から総合的な簿記の力を試される問題が出題されるからです。
自分が今おこなっている作業は何のためなのか?この点について、常に意識しながら問題を解いていきましょう。
最初は時間が掛かってもいいので、時間を計って問題を解いてみる
さきほど述べたように簿記3級の総合的な問題を解く際、最初は帳簿の数字が中々一致せず、何度も計算をし直さなければならない場面がしばしばあります。
解説を読んで理解するのも時間が結構掛かりますし、もう一度問題を解き直すのにも時間が掛かります。
そこで、問題を解く際には毎回必ず時間を計って解くようにしましょう。
最初はどれほど時間が掛かっても構いません。
例えば、当初大問を1つ解くのに60分ほど掛かったとしましょう。
次に同じ問題を解くときは45分。
その次に解いたら30分。
このように時間を計って、練習問題を繰り返し解き続けていると段々と問題を解くスピードが上がってきます。
目に見える形で、問題を解くスピードがあがっていくと、達成感を感じて挫折しづらくなります。
勉強を継続して行うためにはこのように、なるべく目に見える形で進めていくことが重要です。
心が折れそうなときにモチベーションを維持するコツ5選

ここまでは簿記3級で、「心が折れそうになる主な原因」と「合格のための失敗しない勉強方法」を見てきました。
技術的にはこの内容で充分なのですが、長期的に勉強を継続していくためにはメンタルの維持も大切になります。
そこで、ここではモチベーションを維持するコツを5つご紹介します。
- 家以外の場所で勉強をしてみる
- 簿記3級にはどんなメリットがあるか徹底的に調べてみる
- オンラインやオフラインで簿記仲間をつくる
- SNSで勉強ツイートをおこなう
- ゲーム感覚で簿記アプリを使ってみる
どれもすぐに実践できるものばかりなので、少しずつ取り入れていくと良いでしょう。
家以外の場所で勉強をしてみる
家で勉強を続けていると、どうしても集中力が低下してくることがあります。
休憩をしてすぐに気分転換できるといいのですが、家の中はマンガ、テレビ、スマホ、パソコン、お菓子などの誘惑も多く、中々勉強に取り掛かれなくなる人もいます。
それに加えて、オンとオフのスイッチを切り替えしづらく、家族の声がうるさくて集中できないことも多いです。
解決方法はただ一つ、家以外の場所で勉強してみるということです。
図書館に行けば、静かな空間で誰にも邪魔されずに勉強ができます。
カフェに行けば、コーヒーを片手に勉強ができます。
資格試験予備校の自習室に行けば、目標を共有する仲間と同じ空間で勉強ができます。
他にも、電車の移動中、職場の休憩時間、ちょっとした待ち時間など、ちょっとした隙間時間に家以外で勉強できる場所は沢山あります。
どうしても家での勉強に集中できない人は、敢えて外の空間で勉強してみると、意外なほど集中力が続くことに気付くでしょう。
簿記3級にはどんなメリットがあるか徹底的に調べてみる
簿記3級の勉強がどうしても辛くなったときは、取得した後のメリットについて徹底的に調べてみると良いでしょう。
一般的には就職活動や転職活動に役立つと言われていますが、それ以外にも以下のようなメリットがあります。
- 財務諸表が読めることで、会社の経営状態が分かる
- 新聞やニュースの内容が深く理解できる
- 資産形成や株式投資に役立つ
- 上司や社内での評価が上がる
- お金の知識が身につく
- 家計管理に役立つ
- 税理士などの上位資格を目指せる
- 個人事業主や経営者になる道が広がる
- 自分の力で確定申告ができるようになる
他にも、会社によっては簿記の資格を持っているだけで資格手当などがお給料に上乗せされて支給される会社もあります。
簿記3級の取得をしたあとの自分を具体的に想像して、モチベーションを高めていきましょう。
オンラインやオフラインで簿記仲間をつくる
簿記の勉強をひたすら一人で続けていくと時々孤独を感じ、辛くなってくる時があります。
勉強がスムーズに進んでいるときは良いですが、つまずいたときは誰に聞いていいかも分からず、五里霧中の状態になってしまうことも。
そんな時に、すぐに聞ける環境やすぐに聞ける仲間がいたら、とても心強いですし、勉強を続ける意欲も沸いてきます。
オンラインで通信講座を利用している人は、担当の講師にメールやチャットなどでメッセージを送って問い合わせをすることもできるでしょう。
オフラインで資格試験予備校に通っている人は同じ教室の仲間や先生などに気軽に質問ができます。
オンラインでもオフラインでも、同じ目標を持っている仲間と切磋琢磨することでモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
以下に仲間を作りやすいオンラインとオフラインの場所をご紹介します。
- 資格の大原
- LEC東京リーガルマインド
他にも、ここでは紹介しきれないほど沢山のスクールがありますので、それぞれの特徴を比較して自分に一番合いそうな所を選ぶのがベストです。
SNSで勉強ツイートをおこなう
目に見える形で勉強のモチベーションを維持する方法として、SNSで勉強のツイートをするというのは中々効果的です。
「ツイートする」の元々の意味はTwitterに投稿するという意味ですが、自分が勉強してきたことの記録を残すのが目的なので、InstagramやFacebookなどのSNSでも構いません。
「今日はこの単元が克服できた!」とか「ここでつまずいてしまった…」などの投稿をしていると、必ず誰かが見てくれています。
そのため、絶対にやらなくては!と自分に発破を掛けられますし、もし分からない所をツイートしたら、誰かがコメントで教えてくれるかも知れません。
写真なども投稿できるので、自分がまとめたノートや計算結果などを投稿しておけば、過去どこまで何の勉強をしていたかをすぐに思い出せます。
また、皆に応援してもらうことで途中で挫折しづらくなり、継続的に勉強を続けられる可能性が高まります。
SNSに投稿するのは抵抗が…という方もいるかも知れませんが、個人情報を公開するわけではないのでそこまで警戒する必要はありません。
自分の備忘録としても役立つときが来ると思うので、一度やってみる価値はあるかと思います。
もしひと通り勉強が終わったら、投稿を削除してしまっても構いません。
ゲーム感覚で簿記アプリを使ってみる
最後に、ゲーム感覚で楽しみながら勉強できる簿記アプリについてご紹介します。
今ではほとんどの人がスマートフォンを所有しており、わざわざパソコンを開かなくても、いつでもどこでも気軽にアプリで勉強ができる時代です。
もちろん、簿記などの勉強アプリも充実しており、電車やバスでの移動中、職場での休憩時間やちょっとした隙間時間に勉強ができます。
書くのがあまり得意ではない人、デジタル機器に慣れている人、ゲームが好きな人などは、アプリでの勉強を組み合わせるとモチベーションを維持しやすいかもしれません。
ただし、アプリは手元で操作しやすいというメリットがある一方、簿記の内容を体系的に理解するツールとしては向いていません。
あくまでもテキストの内容をすべて学習した後に、補助的に使用するツールであるということを忘れないでください。
ここでは無料で使えて簿記3級の勉強に役立ちそうなアプリを3つご紹介します。
パブロフ簿記3級lite
パブロフ簿記liteアプリの特徴は以下の通りです。
引用:パブロフ簿記のアプリ(1級、2級、3級) | パブロフ簿記 (pboki.com)
- 最新(2022年度改定)の試験範囲に対応している
- スキマ時間に勉強できる(オフラインで利用可能)
- すぐにマネできる解き方が書いてある
- 実務経験に基づいた、わかりやすい解説
- 「パブロフ流」解説付き60分の実践問題が無料ダウンロードできる
- ネット試験の模擬問題が利用できる
スマホのアプリとはいえ、かなり内容が充実しています。
試してみて自分に合わなかったら使わなければいいだけなので、気になる人は是非ダウンロードして使ってみましょう。
簿記3級 解説付き問題集
あまりアプリっぽい名前ではないですが、れっきとした簿記アプリです。
簿記3級 解説付き問題集の特徴は以下の通りです。
参考:「簿記3級 解説付き問題集」をApp Storeで (apple.com)
- 基本から分野別、出る順までたっぷり796問題。
- 全問題に丁寧な解説付き
- チェックを入れた問題を後からまとめて復習できる機能付き
シンプルで使いやすく、問題数も充実していますね。796個の問題を解き終えたら、かなり力がつきそうです。
仕訳簿記3級
アプリのタイトル名通り、簿記3級の仕訳に特化したアプリです。
仕訳簿記3級の特徴は以下の通りです。
引用:「仕訳簿記3級」をApp Storeで (apple.com)
- 直感的に簿記の仕訳の知識が身につく
- 苦手な問題の傾向をアプリが認識し、問題を出題
- 短時間で効率的に簿記を学習
他のアプリと違って仕訳の時に画面をスワイプして回答するため、直感的に仕訳の概念を指先で感じることができます。
まさに、スマホの特徴を最大限に活かしたアプリと言えるでしょう。
学習内容も仕訳に特化しているので、仕訳が苦手な人には特にオススメのアプリです。
正しい勉強方法を続けて、モチベーションを維持することが大事
簿記3級の内容は、簿記を勉強し始めた人が最初に学ぶべき超重要な内容がギッシリと詰まっている資格です。
ですが、間違った勉強方法を続けていると、モチベーションにも影響を及ぼし、心が折れそうという状態に追い込まれてしまいます。
そうならないためにも、今回紹介した正しい勉強法を続け、モチベーションを高く維持したまま簿記3級の本試験に臨みましょう。
正しい勉強法も、モチベーションを維持するコツも、ほんのちょっと工夫をするだけで誰でもすぐに実行できる内容ばかりです。
日常生活に少しずつ取り入れて簿記3級合格を無理なく目指していきましょう。
簿記3級講座の比較表
| CPA会計学院 | クレアール | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 3,850円 | |
| 割引 | × | 合格でAmazonギフト500円 | 資料請求で9,600円 |
| 質問 | × | 1回1,100円 | 無制限で可能 |
| 特徴 | 資料請求で動画講義/テキスト/問題集が貰える | スマホで倍速視聴 | 合格範囲の効率学習 |
| 実績 | × | 年間合格1,000人超 | × |
| 公式 | 無料の資料請求 | 無料の資料請求 |